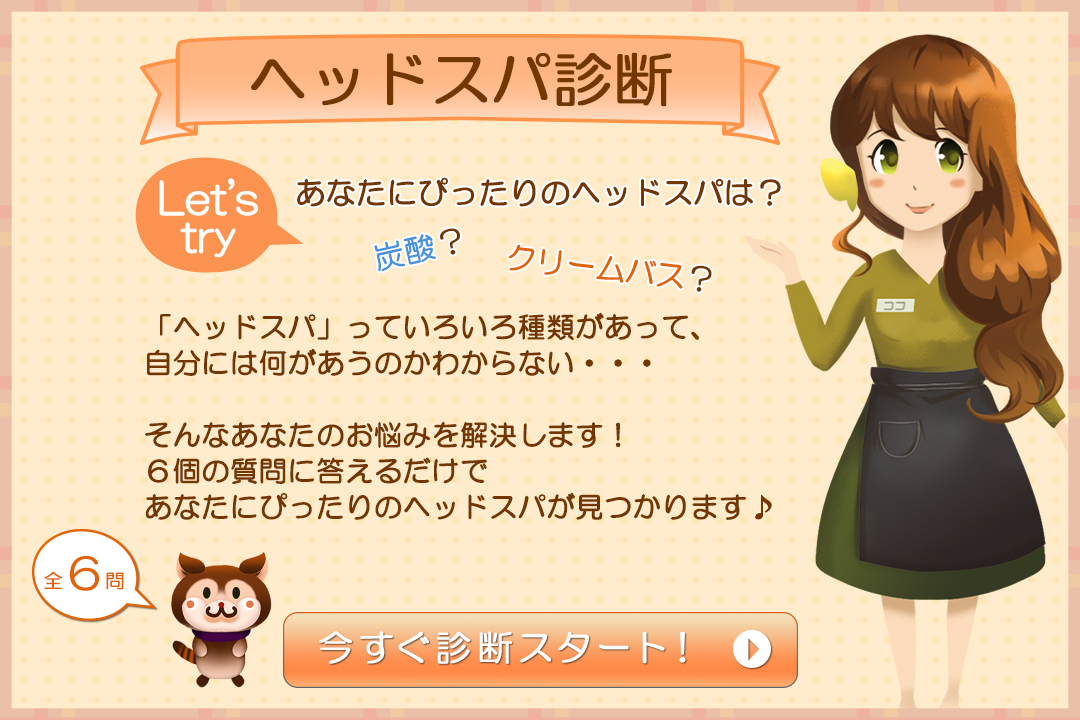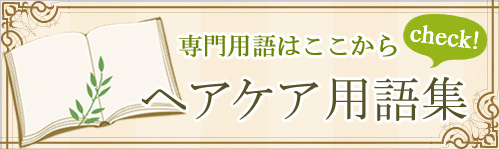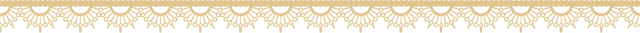- ヘッドスパ 頭美人 TOP
- >
- ヘアケア講座
- >
- 頭皮ケア(スカルプケア)の講座
- >
- フケが発生する原因と対策
- >
- ペットから感染?頭の水虫(頭部白癬)の症状・治療・家庭での対策
本ページはプロモーションが含まれています
フケが発生する原因と対策
ペットから感染?頭の水虫(頭部白癬)の症状・治療・家庭での対策
Infect from pets! What is a head athlete's foot?

ペットから感染する「頭の水虫」は何?
頭の水虫は医学的には頭部白癬と呼ばれる、白癬菌が頭髪に感染して起こる病気です。
猫や犬に多いMicrosporum canisなどの菌が人へ伝わり、円形の脱毛や細かいフケが増えるといった症状が出ます。
脂漏性皮膚炎や円形脱毛症と似て見えてしまうことがあり、独断での市販薬対応は遠回りになりやすい点に注意しましょう。
症状の特徴と誤診されやすいポイント
境界のはっきりした脱毛斑が現れ、表面に細かな鱗屑が付くのが典型的です。
毛が表面で切れて黒い点のように見えることがあり、炎症が強いと盛り上がって痛むケルズス禿瘡に進むこともあります。
フケやかゆみだけに見えても、脱毛斑や折れ毛があれば白癬を疑って受診してみましょう。
どうやってペットからうつるの?
白癬菌は皮膚や毛に付着しやすく、感染した動物との直接接触でうつるほか、寝具やブラシ、カーペットなど環境に落ちた毛や皮膚片から間接的に広がることもあります。
動物側は無症状の保菌状態である場合もあり、知らないうちに人へ伝播することがあります。
家の中での密接な接触や共有物の共用が多いほど、家庭内での連鎖が起こりやすくなります。
うつりやすい場面と、すぐできる予防
動物を抱っこした直後に顔や頭を触る、同じ寝具で一緒に寝る、ブラシやタオルを共用する、といった場面は感染リスクが高まります。
触れ合いの後は石けんと水で手洗いを徹底し、過度な濃厚接触(口移しでの給餌や顔まわりを舐めさせる等)は避けましょう。
子どもや高齢者、皮膚に傷がある人はとくに注意が必要です。
受診から治療までの流れ
皮膚科では、KOH直接鏡検や培養などで原因菌の有無と種類を確認します。
治療の主役は内服の抗真菌薬で、外用薬だけでは十分な効果が得られにくく、悪化した報告もあるため原則として推奨されません。
補助として硫化セレンなどのシャンプーを併用し、毛髪に付く胞子を減らして周囲への拡大を防ぎます。
治療期間は数週間〜数か月と幅があり、通院で経過を見ながら調整します。
菌種別の治療の考え方
Trichophyton属が原因の例ではテルビナフィン内服が選択されることが多く、比較的短期間での管理が期待できます。
一方、Microsporum属が原因の例では、グリセオフルビンを含む他の選択肢が検討されることがあります。
年齢や体重、肝機能、薬の相互作用などに配慮して、医師が最適な薬と期間を判断します。
家庭でやるべき感染対策
まずは「清掃→消毒」の二段階で環境を整えます。
毛やフケを**取り除く清掃**として、よくいる場所の掃除機がけ、拭き掃除、ゴミは密閉破棄を徹底します。
続いて**消毒**として、製品表示で真菌(Trichophytonなど)に有効と記載された消毒剤を、取扱表示に従って使用します。
タオルや寝具、帽子、ブラシ、ヘルメット内装などはこまめに洗濯・交換し、共用を避けましょう。
共有物・生活動線の見直し
タオル、枕カバー、くし、帽子は個人専用にし、洗濯頻度を上げます。
床やソファ、カーペットなど毛が残りやすい場所は、掃除機と拭き取りを組み合わせます。
浴室のマットや脱衣かごも定期的に洗浄・乾燥させ、湿った環境を放置しないようにしましょう。
ペット側のケアと生活ルール
疑わしい皮疹や脱毛が見られたら、動物病院で診察と治療を受けさせましょう。
同居動物にも症状がないかチェックし、獣医師の指示のもと治療と環境対策を同時に進めます。
回復までのあいだは過度な密接接触を控え、触れ合いの後は手洗いを習慣化します。
よくある疑問(FAQ)
Q: 治療はどのくらい続きますか?
反応や菌種によって異なりますが、数週間〜数か月が目安です。
短くても油断せず、医師の指示通りに内服を継続し、再発を防ぎましょう。
Q: 市販の塗り薬やフケ用シャンプーだけで治りますか?
頭部白癬は毛包まで関与するため、外用単独では不十分です。
医師の管理下で内服治療を受け、補助的にシャンプーを活用しましょう。
Q: 家の掃除は何から始めれば良いですか?
まず毛やフケを取り除く清掃(掃除機・拭き取り)を行い、その後で真菌に有効な消毒剤を使う二段階が基本です。
共有物の洗濯と個別管理も同時に進めると効果的です。
Q: ペットは元気ですが、人にうつすことはありますか?
あります。
動物は無症状で保菌していることがあり、家族への拡大を防ぐためにも獣医師の診察と環境対策を並行しましょう。
まとめ
猫や犬からうつる頭部白癬は、**早期受診と内服治療、そして家庭の環境対策**が回復の近道です。
今日からは、触れ合い後の手洗い、共有物の管理、清掃→消毒の二段階をルーティンにしましょう。
ペットの診療と人の治療を同時に進めることで、再感染の不安をぐっと小さくできます。
おすすめのアイテム COMP Gummy TB トータルバランスドモデル

記事が気に入ったら「いいね!」お願いします。
頭美人では、髪や頭についての気になる記事をご紹介!
頭皮ケア(スカルプケア)の講座
頭皮ケア(スカルプケア)の講座