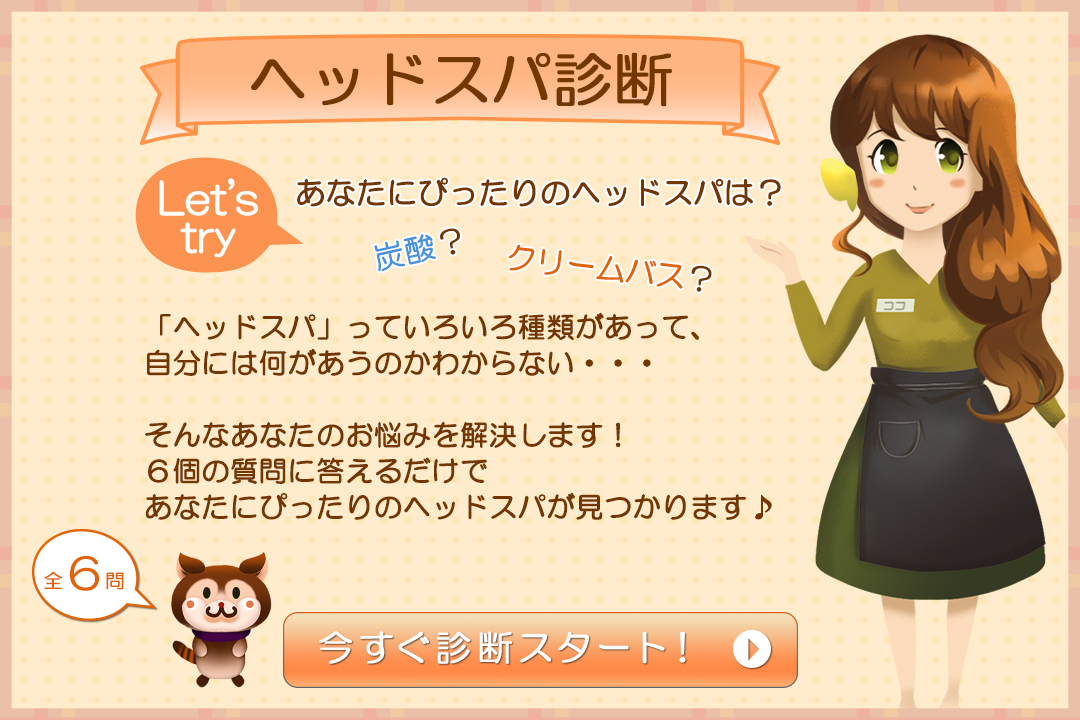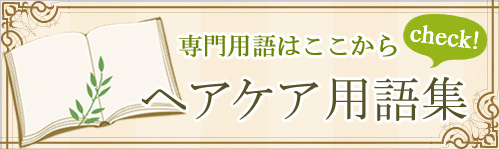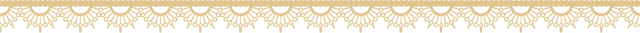- ヘッドスパ 頭美人 TOP
- >
- ヘアケア講座
- >
- 日常のトラブル
- >
- 食生活について
- >
- 食べ過ぎが髪に与える本当の影響!翌日からのリカバリー完全ガイド
本ページはプロモーションが含まれています
食生活について
食べ過ぎが髪に与える本当の影響!翌日からのリカバリー完全ガイド
The effect of over eating on hair.

食べ過ぎが髪に及ぼすメカニズム
食べ過ぎはその場の満足感に対して、頭皮や髪にはジワジワ不利に働くことがあります。
とくに脂質・塩分・高GIの糖質がかたよって多くなると、皮脂バランスや血管循環、ホルモンの働きが乱れやすく、頭皮の炎症やベタつき、抜け毛リスクの土台を作りやすいのです。
ここでは「なにが、どう髪に響くのか」をやさしく整理します。
脂質過多は皮脂バランスを崩しやすい
動物性脂肪や揚げ物が続くと、皮脂が増えやすく、毛穴の詰まりや頭皮の炎症を招きやすくなります。
皮脂組成や分泌量の変化はニキビなど皮膚炎症の悪化要因とされ、頭皮でもフケやかゆみ、ベタつきの連鎖につながります。
炎症が慢性化すれば、毛包環境の悪化を通じて抜け毛リスクが高まることもあります。
過度な脂質が“即ハゲる”という単純な話ではありませんが、皮脂の過多は頭皮トラブルの温床になりやすい点は押さえておきましょう。
塩分過多は血圧・循環に負担
塩分のとり過ぎは血圧上昇の一因です。
高血圧は全身の血管に負担をかけ、末梢の微小循環にも不利に働きます。
頭皮も例外ではありません。
麺類のスープを飲み干す、漬物の回数が多いなどの積み重ねは、まずは全身の健康面で見直していきたいポイントです。
糖質過多と高GIはインスリン経由で皮脂・炎症に影響
高GIの食事は血糖を急上昇させ、インスリン分泌を促します。
皮脂分泌や炎症関連シグナルと結びついてニキビを悪化させることが示されており、頭皮でもベタつきや毛穴トラブルを助長しやすい土台になります。
また、IGF-1など成長因子は毛包にも関わる一方、過剰な糖質習慣はホルモン・代謝の揺らぎを通じて皮脂や炎症に影響しやすいと考えられます。
「甘い物=すぐ薄毛」の直線関係ではありませんが、皮脂・炎症を介した遠回りの影響には注意しましょう。
暴飲暴食は消化吸収を落として栄養が届きにくい
食べ過ぎ・飲み過ぎが続くと胃腸に負担がかかり、必要な栄養素の消化・吸収効率が下がりがちです。
結果として、タンパク質や鉄、ビタミン・ミネラルが十分に毛根へ届かず、髪のツヤ低下や抜け毛の土台になります。
食べ過ぎ自体よりも「かたより+吸収低下+皮脂・炎症」の複合が、髪にボディブローのように効いてくると覚えておきましょう。
髪に現れるまでのタイムラグ
髪は肌よりも反応が遅く、生活の変化は数週間〜数か月ずれて現れます。
成長期・退行期・休止期というヘアサイクルがあるため、食生活の改善も“今日やって明日フサフサ”とはいきません。
目安として、食事を整えてから2〜3か月は土台づくりの期間と捉え、まずは頭皮のベタつきやフケ、かゆみの改善サインをチェックしましょう。
体質(AGA/FAGA)との交差
遺伝・体質に由来する薄毛(AGA/FAGA)はホルモン感受性が関わります。
食事だけでコントロールするのは難しい一方、皮脂や炎症、循環、栄養状態の“悪化要因”を外しておくことは、治療の足を引っ張らない意味で重要です。
気になる場合は早めに専門医へ相談しましょう。
食べ過ぎた日の翌日からできるリカバリー
「やってしまった…」翌日は、低GI・高たんぱく・野菜・水分の“4点セット”で立て直します。
糖質は控えめに質を選び、脂質は魚・ナッツなどの良質なものを少量、塩分は薄味を徹底。
胃腸を休ませる意識も大切です。
低GI・高たんぱく・野菜・水分の基本
主食は雑穀・オートミール・玄米・全粒粉などに置き換え、血糖の急上昇を避けます。
たんぱく質は魚・鶏胸・大豆製品・卵を中心に。
野菜・海藻・きのこで食物繊維とミネラルを補い、こまめな水分で循環を助けます。
コンビニで即実践メニュー例
雑穀おにぎり+サラダチキン+海藻サラダ+納豆。
無糖ヨーグルト+ゆで卵+ミニトマト+アーモンド少量。
ツナ缶(水煮)+カット野菜+豆腐+味噌汁(汁は控えめ)。
外食・宴会での守り方
揚げ物・濃い味は「最初のひと口で満足作戦」、おかわりはしないと決めます。
サラダ・刺身・湯豆腐・焼き魚など“胃にやさしい順”で注文し、麺類のスープは残すのが基本。
塩辛や漬物、濃い煮物は量を絞り、アルコールは水と交互に。
夜食とアルコールの賢い線引き
就寝直前のドカ食いは睡眠の質を落とし、翌日の食欲ホルモンにも響きます。
どうしても空腹なら、無糖ヨーグルト・豆腐・味噌汁など軽めで済ませ、アルコールは“ほどほど+水”を徹底しましょう。
栄養・サプリの正解と落とし穴
髪は「不足の補正」が基本です。
鉄・ビタミンD・ビタミンC(鉄吸収を助ける)などは不足しやすく、検査で不足があれば補いましょう。
“何となく”の多種大量摂取はおすすめしません。
不足しやすい栄養と食材例
鉄(赤身肉・レバー・あさり・小松菜)、ビタミンD(青魚・きのこ・日光)、亜鉛(牡蠣・牛赤身・大豆)、たんぱく質(魚・鶏胸・卵・大豆)などを、毎日の食卓で少しずつ積み上げます。
サプリは検査と食事で足りない部分をピンポイントに。
過剰摂取は逆効果になることも
ビタミンA・E・セレンなどは過剰で脱毛リスクの報告があります。
「髪に良い」を根拠なく増やすほど髪が減る、という皮肉を避けましょう。
まずは不足確認、つぎに最小限の補正が鉄則です。
受診・検査の目安
抜け毛が急に増えた、分け目が広がる、頭皮炎症が続く、月経の乱れや慢性疲労を伴うなどは、一度血液検査で鉄・フェリチン、ビタミンD、甲状腺などを確認すると安心です。
自己判断での極端な制限や過剰摂取は避けましょう。
生活習慣で“頭皮に回す余力”をつくる
食事が整っても、睡眠不足や運動不足、喫煙、強いストレスがあれば頭皮に回る余力は目減りします。
基本の生活を軽く底上げして、髪の伸びしろをつくりましょう。
食べる時間帯と睡眠の関係
深夜の満腹は睡眠の質を落としがちです。
夕食は寝る2〜3時間前までに、就寝前は消化にやさしい軽食で済ませます。
起床後は朝日を浴び、体内時計を整えてホルモンのリズムを安定させましょう。
腹八分目を続ける小ワザ
最初の5分はゆっくり、野菜と汁物から、主食は小盛り、よく噛む、テーブル上に追い調味料を置かない、外食は単品より定食でバランスを取る——小さな工夫の積み重ねが効きます。
軽い運動で血流サポート
食後のゆるい散歩、階段利用、ストレッチは立派な“血流ケア”です。
週合計150分の中強度運動を目安に、無理なく続けましょう。
NGと誤解の訂正
「糖質ゼロにすれば解決」ではありません。
極端な糖質オフは栄養バランスを崩し、かえって不調を招くこともあります。
GIを下げつつ、質の良いたんぱく質・脂質・食物繊維で“整える”のがコツです。
また「髪に良い食材の食べ過ぎ」も逆効果。
特定の栄養だけを大量にとっても、吸収や代謝には限界があり、過剰はかえってマイナスです。
FAQ
Q: 甘い物を食べ過ぎると薄毛になりますか?
直接“甘い物=薄毛”とは言えませんが、高GIの食習慣は皮脂や炎症を通じて頭皮トラブルを招きやすく、結果として髪に不利に働く可能性はあります。
頻度と量を見直し、低GI中心へ切り替えましょう。
Q: 塩分のとり過ぎは髪に悪いの?
塩分過多は高血圧のリスクを高め、全身の循環に負担をかけます。
頭皮も体の一部ですから、まずは健康のために減塩を意識することが髪にもプラスです。
Q: プロテインの飲み過ぎは抜け毛の原因?
たんぱく質は髪づくりに必須ですが、量や脂質の質が過剰だと皮脂バランスを崩
おすすめのアイテム 髪質改善サロン オールインワン サロンシャンプー

記事が気に入ったら「いいね!」お願いします。
頭美人では、髪や頭についての気になる記事をご紹介!
日常のトラブル
日常のトラブル